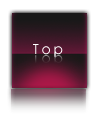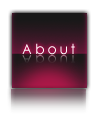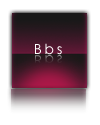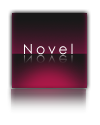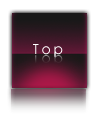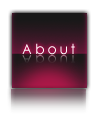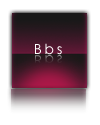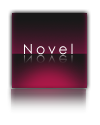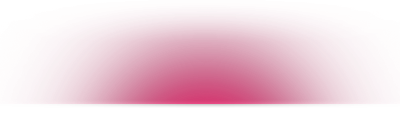東方短編集 〜The Different Story
#16 胡蝶の幻想
都合の良い夢が見たくて。
この現に戻ってこられないように。
その時、私を呼ぶ声がした。
暑い陽射しの日々が過ぎ去り、
肌寒い紅葉の日々が過ぎ去り、
真っ白な雪の日々が過ぎ去り、
そして、春の季節がやってきた。
隙間を操る妖怪、八雲紫はそんな季節の変わり目を感じて感慨深く咳をついた。
春の季節の象徴たる、桜の花びらが優雅に、けれど哀しげに舞っていた。
それはまるで、雪から桜に変わったように。世界が桜に覆われてるような、そんな錯覚すら感じた。
「…………」
実の所、八雲紫は寝坊した。
桜 は散る前の満開時が美しく、素晴らしいと知っていた筈なのに。
それにも関わらず"寝坊"してしまったのは、つまるところ、「寒かった」としか言えなかった 。
寒かった故に、花見シーズンから少し遅れてしまった。
しかしどうだろうか、そんな寝坊した大妖怪の前には、それこそ一番美しい時を逃したのにも関 わらず、淡い薄紅色をした綺麗な花びらが舞っているのだ。
散っていなかったら、どんなに綺麗だったか。
これ以上の美しさを、見れなかった事に若干の後悔をして、少しの間、八雲紫はそんな桜の木を見つめていた。
「────」
紫は静かに目を閉じた。
頬を撫でるような柔らかな風が吹いていて、気持ちが良い。そして風に運ばれた、春の匂いが鼻孔を掠め、新鮮 な空気が体内を蹂躙し、ある種の清々しさを感じて、
紫はゆっくりと目を開いた。
「春が、来たのね」
そっと呟いて、
今度は藍とここで花見をしようかな、と考えて、お気に入りの日傘をくるくると楽しげに回しながら、桜の木の森を歩いた。
少しの間歩くと、見渡しの良い開けた場所に着いた。
真ん中に大きな桜の木が堂々と生えていて、そこから遠ざかるように桜の木が生えていた。
ま るでこの桜の森の長かと思うような、大きな桜の木には桜の蕾しか実っておらず 、そこだけが少しだけ時間がずれているような、そんな気がした。
ここで花見をしよう。
紫はそう考えて、くすりと笑みを浮かべて、そして何処からか聞こえてきた足音に気付いて、隙間の中へと消えていった。
◆ ◆ ◆
夜。
夕暮れの橙が過ぎ去り、空は闇に覆われる。
まるでそれは天蓋のように。紙芝居のように。
決まった時間に闇に染まる、その様は、如何にも誰かの意図によって操作されてるのではないか。
その誰かが、人知の超えた存在だとしたら。どうだろうか。
「藍には悪いけど」
いや、そんな存在はありえないのかも知れない。
存在、というよりはそれは法則みたいなものだから。
奇跡的な数字が重なり合って、この地上があるのだから。
軌道上の些細なズレは崩壊を生む。
「夜桜もいいわね」
そのズレさえも無い、その計算されつくしたこの地上のシステムは、
いやシステム自体が、まさしく人知を超えた存在。
私達が知覚することすら出来ない、そういった別次元の話。
「…………」
私はそれを、ある目的を持って。実現させようとしている。
理想郷。誰もが平等に、そして助け合えるような、そんな楽園を。
そんな目的を掲げて、自分は本当に自分なのかと問う時がある。
何でそんな事をするの。この能力さえあれば世界ですら自分の手の内だというのに。
けど、しなかった。出来なかった。
妖怪、いや大妖怪となった今でもそんな事は出来なかった。
「あら、先客かしら──」
この世界には楽しいことが満ちているのだから。
そう、世界には楽しいことが満ちている。
その反面、世界には哀しいことも満ちている。
だから、私は楽しいことが満ち溢れた世界が創りたい。
違う、そうじゃなくて。
見てみたい。その世界を、その世界で暮らす人々を。
「……」
大きな桜の木の下に、一人、着物を着た女性がいた。
白い着物に、薄紅色の帯。その後姿が、とても綺麗で。
風がはらりとそよぐ度に、女性の黒い髪がさらりと揺れる。
大きな桜の木の上には丸いお月様が一つ。その姿を照らすかのように、輝いていた。
八雲紫はその姿に呆気にとられ、少しの間言葉が出なかった。
「……」
彼女は、人間だろうか。
そんな疑問すら浮かんだ。
桜の花びらが舞う。
彼女は、妖怪だろうか。
そんな疑問も浮かんだ。
妖怪が跋扈するこの夜の刻に、彼女は一人で桜の木を見上げていた。
風がはらりと吹く度に、桜が舞い上がって、そして落ちていく。
その中心に彼女はいて、その彼女は桜の花を咲かせない木を見上げていた。
そんな彼女が不思議で。
そして、気になったのだった。彼女の事が。
声が出なかった。
違う。
そうじゃない。
声を出そうとした。
「ここにいらっしゃったのですか」
しかし中を舞ったその声に八雲紫は隙間の中へと消える。
それは凜とした、力強い、男の声だった。
彼女の配偶者だろうか、と紫は考えて、そして隙間を完全に閉ざす。
闇。
そして、灯り。
まるで今まで幻想の光景を見ていたかのように。
自分の家に着いたときに、未だにあの光景が浮かぶのだった。
桜を見上げる少女の姿を。
それが頭から離れなくて、もう一度隙間を開いてあの場所に行こうかと考えて、そして止めた。
きっと。
きっと明日もくる。そんな気がしたからだ。
あの桜の木の下で、花を咲かせない木の元で、
彼女はまた見上げるのだろう。
だから明日、またあの場所に行こう。
八雲紫はそう考えて、はあ、と息を吐く。
◆ ◆ ◆
「花見は皆でするものよ、一人じゃ寂しいじゃない」
次の日の夜も、彼女はそこにいた。
だから私は意を決して声を掛けてみたのだった。
妖怪らしく。隙間から身体を覗かせて。
彼女の上から、気怠そうな声で。
「あなたは──。妖怪さん?」
隙間から顔を覗かせるなんていう、心臓が弱い人がみたら卒倒しそうな光景を、
彼女は意に介さず、まるで新しい友達が出来たかのような口ぶりで訊いた。
「ええ、そうよ。とっても怖い妖怪さんよ」
にこやかに笑みを作って、八雲紫は扇を広げて口元を隠す。
目を細め、彼女に対して睨みを利かせても怖がらないので「なんだ怖くないのね」と溜息をついた。
そんな紫は彼女を注意深く見ていた。
昨日と違う着物を着ていたが、それ以前に彼女の肌の白さに驚いた。
病的なまでに白いそれは、昼間から外を出ずにずっと家の中にいるという事だろう。
「妖怪さん、ここは危ないわ」
「そう。注意しておこうかしら」
そして何よりも、妖怪に対して驚かないという事だ。
普段から妖怪を見慣れているのだろうか、それとも彼女が妖怪だからだろうか。
いや後者は違うだろう。彼女は人間なのだろう。わざわざ妖怪が妖怪に対して妖怪さんなどと呼ばない。
「そうだ」
桜の木から視点を少し変えて、彼女は八雲紫を見上げる。
「あなたのお名前を聞かせてくれないかしら?」
「八雲紫」
くすっと笑って、その問いに答える。
「やくもゆかり」
彼女もその名を噛み締めるように呟いて、
「私は、西行寺幽々子。よろしくね。紫」
西行寺幽々子。
その名前に八雲紫ははっとする。
彼女はあの法師の娘ではなかろうか。
だとすると何故ここにいるのか、分からなかった。
いや寧ろ、こんな桜の森にいるのは俗世との縁を切るためだろうか。
思考する。
しかし何も答えは出なかった。
「幽々子。また明日もここにいるかしら?」
「ええ、きっと」
自然と幽々子とは名前で話していた。
それは何となく、彼女と気が合いそうな気がして、
貴女と一度会ったことあったかしら?と尋ねてしまいそうだった。
そして幾ばくか時が過ぎて、
「それじゃ」
「また明日」
二人はお互いの家へと帰っていく。
「紫のそれ、便利ね」
「皆そう言うのだけど扱いづらいのよね。ほら、リボンを結ばなきゃこの隙間がどうなるか分かったもんじゃないし」
◆ ◆ ◆
「西行寺幽々子……?」
あれから屋敷へ戻り、式神に検索をかけたのだった。
藍がそれより晩御飯にしませんかと言っていたが、無視。
はあ、と溜息をついて藍は少しの間考える素振りを見せて、
その問いに対して都合が良かったのか、それとも性能が良かったのか分からないが、その答はすぐに出たのだった。
「その名前。訊いた事あります」
藍が思い出したように言った。
「なんでも、死へと誘う少女だとか」
西行寺幽々子。
死へと誘う少女。
忌み嫌われた能力の持ち主。
「死へと誘う、ねえ……。なんともなかったけど」
「紫様、お会いになられたのですか!?」
「まあね」
その能力を持って、彼女は何を思うのだろうか。
寂しくは無いのだろうか。
悲しくは無いのだろうか。
彼女はそれでも、笑みを浮かべていた。
それは、久々の話し相手だったから……?
◆ ◆ ◆
八雲紫の、西行寺幽々子に対する関心は、
まるで妖怪と人とが親しくなるようなそれとは少し違ったような、気がした。
そう考える八雲紫の式、九尾の妖である藍は、紫の仕組んだプログラムから外れた思考をする。
前の幻想郷と同じように、紫は寝坊し、そして西行寺幽々子に出会う。
それからの出来事もうっすらとだが覚えている。
何も変わらずに、また巡っている。ならばそれでいいじゃないか。
「それで、いいのか……?」
考える。
紫の考えている事を。
今までのようにやってはいけない。
ただ言われることをこなすのではなく、
言われることを予想してやっておく、という考え方へ。
それはある程度の歴史を手に入れた藍にとって、容易いことであり、
しかし今までやったことがない式としての藍にとっては難しいことこの上ない事だった。
その先見は八雲紫と西行寺幽々子が出会うその時じゃなく、
八雲紫が、藍を隙間へと送った気の遠くなるような将来の事で、
そしてそれは過去の事であり、藍は自分自身を隙間へ送った後、
つまりは前の彼女が言っていた、
「私が向かうのは始まりではなくて終わりよ、貴女は来るべきじゃない。」
その言葉の真意を確かめるべく、藍は密かに息を潜めて、思考する。
◆ ◆ ◆
夜はね、妖怪の時間なの。
西行寺幽々子が云う。
そうね、なら昼時に現れる私は人間だったりして。
八雲紫が茶化す。
「私はね、紫が人間でも疑わないわ」
桜の花びらが舞うなか、幽々子が紫を見上げて呟く。
「えっ……」
その言葉が意外だったから。
そして自分の同一性が、何か内側から締め付けられるような、そんな感覚がした。
人間と妖怪。その境界は一体何であろうか。
境界を操る私は、一人一種族の妖怪。
けれど、それは妖怪たる何かが無ければ人間という存在になるのではないか。
「紫はどっちが良い?」
「そうね──」
妖怪の資格とはなんだろうか。
特別な力を持っていること?
ならば目の前にいる彼女は人間では無くなる。
妖怪の資格とはなんだろうか。
人の姿をしていないこと?
ならば私は一体何者なのか。
「秘密」
扇子で口元を隠し、意味ありげにくすりと紫は笑う。
紫陽花の絵が描かれた扇子が映し出される。
「あら、綺麗」
それが鮮やかで、目を見開いて、幽々子が紫のそれを指差す。
「ありがと」
果たして私は一体何者であろうか。
その答は出なかった。
その次の日に八雲紫は幽々子の屋敷へと赴くことにした。
理由は特に無い。強いて言うのであれば、それは幽々子に対する興味である。
彼女が屋敷でどんな生活をして、どんな事を思っているのか。
それが知りたかったからであった。
「妖怪風情が、この屋敷に何の用だ」
そう、だからこんなところで足止めを食らうなんて思っても見なかった。
そもそも。と紫は思う。
この屋敷の中に隙間で入っていれば面倒な事には無かったのであった。
わざわざ、(というのも、幽々子が屋敷で一人で生活をしていると思っただけに)正面から入るなんてことさえしなければ。
と若干の後悔と目の前にいる「面倒なもの」の煩わしさに、はあ、と溜息をついた。
それは初老の男性であった。
袴を着て、堂々と屋敷の玄関前で、その双眼を妖怪へと睨み付けていた。
凄腕の武士だったのであろうか、未だに立ち振る舞いがしっかりしており、
紫相手に隙を見せておらず、いつでも腰に下げた刀を抜ける状態でこちらの様子を伺っている。
返答次第では斬る、ということだろうか。
紫自信としては、遊びに来たわけで戦いをする気分でもなく。
また一つ溜息をついて。
「遊びに来たのよ。通してくれないかしら」
と言っても、通してくれないのは明白であって。
暫くした後、屋敷の前での喧騒に気づいた幽々子がやってきて、やっとの事で屋敷の中に入ることが出来たのであった。
「でも驚いたわ。紫が私の屋敷に来るなんて」
幽々子が興奮した様子で紫に話しかける。
彼女曰く、屋敷に人が訪れるなんて久しぶりだと言っていたせいか、声に歓喜の色がこもっていた。
そんな幽々子の後ろには屋敷の前で立ち塞がった初老の男性。魂魄 妖忌が一定の間を取りながら音も立てずに付いてきた。
「暇つぶしよ、暇つぶし」
幽々子に案内されたのは屋敷の縁側だった。
しんと静まり返っていて、風のそよぐ音だけが聞こえた。
そこから見える風景は、桜。
幽々子と初めて出会った場所でみた桜と、ちょっとだけ違うようなそんな桜。
「ここから見える桜も綺麗でしょう?」
嬉々と喋る彼女は思わず顔を綻ばせ、笑みを浮かべて紫に問いかけた。
それは紛れも無い普通の少女であって、何か特別な能力をもつような、
そう、死へと誘うような恐ろしい能力をもつ少女には見えなかった。
「ええ。そうね」
だから、ここから見える桜を少しでも長く見ていようと思ったのだった。
「幽々子殿」
あれから暫くした後、唐突に紫は帰ると言ってあっという間に帰ってしまった。
それこそが八雲紫らしく、自由奔放で、羨ましい。と幽々子は思っていた。
そんななか紫が座っていたところを見ながら呆けていたら、後ろから妖忌がお茶を差し出した。
「彼女は一体」
「友達よ」
「左様で」
出されたお茶を手にとって、そっと口をつける。
妖忌の出すお茶は渋みがあって、まだ寒さが残る春には丁度良かった。
夕刻の空が綺麗な茜色に染まり、屋敷から覗かせる四角い風景は色を朱に染めていった。
「彼女は妖怪です。もしかしたら幽々子殿のお命が──」
「化け物の首を取るなんてこと、妖怪でもしないわ。彼らだって命が惜しいもの」
「しかし……」
「それでも、私に近付くなら。そこに悪意があったとしても私は嬉しいのよ」
そう、私は化け物なのだ。
人間でも妖怪でも無い。それすら畏怖する存在。
死へと誘う女なのだから。
世間でも疎まれ、妖怪からも怯えられ、この地でひっそりと暮らしてきた。
ある目的を達して、そして自分はこの地で消え去ろうと。
だから八雲紫という存在は常識外。
非常識の存在であった。
彼女が見ている世界とは、どんなものなのか。
私が見ている灰色の世界から、色鮮やかな世界へと連れて行ってくれるような気がして。
けど、それは叶う事が無いことも分かっていた。
私にはやらなくていけないことがある。
だから。この出会いはきっと私の猶予の期間。
これが私の残された時間。
「……桜、綺麗ね」
「ええ――」
いつまでもこんな時間が続けばいいのに、と。
初めて思うのだった。
ゆくへなく月に心のすみすみて
果てはいかにかならんとすらん
そっと、それを口ずさんで、
静かに目を閉じる。
――どこまでも月に心が澄んでいき、この果てに私の心はどうなってしまうのだろうか。
……今の私に合った短歌であった。
どこへ向かおうとしているのか。
少し冷えた風が、頬を掠めて、心臓を擽られる感覚にもどかしさを覚えて。
そのもどかしさこそが、今の心中なのだろうと気づいた。
「寒くなってきましたな、戸を締めて参ります」
◆ ◆ ◆
「まだいたのか」
「桜が綺麗でね」
妖忌が屋敷の戸を閉めていると、とある庭の一角で八雲紫を発見したのだった。
親指で鞘から刀身を少しだけ出して、いつでも抜ける状態にしたその時のことだった。
「私には分かりませんな、紫殿」
「あら、貴方の方が彼女より分かるのではないかしら?」
縁側で刀に手をかける者と、
庭で傘をさして桜を見上げる者、
妖忌は目を細めて眼前の妖怪を凝視していたが、彼女の方はそんな視線を無視して桜を見上げていた。
まるで妖忌が彼女にとって取るに足らない人物のように、
彼女は平然と、そして、思い出したように、呟いた。
「あの桜の木には誰が埋まっているのかしら」
止まった。
紫と妖忌。二人以外、何もかもが止まった。
桜の花びらは静寂を保ち、瞬きすらも忘れてしまう。
ごくり、と喉が鳴った。
「勿論、この桜の木。じゃないわよ」
彼女の注釈は妖忌を更に追い詰める。
彼から除かせる紫の表情は見えなかった。
見えないからこそ、図りかねていた。
「桜の木の下に、誰が埋まっている?聞いたことありませんな」
平然とした口調で答える。
この妖怪は何を考えているのか。
そして何が目的なのか、分からなかった。
「そう……。ならいいわ」
そして彼女は風に攫われるかのように消えた。
心をば深き紅葉の色にそめて
別れゆくや散るになるらむ
さあ、心を真紅に染めて、
お別れをしましょう。
それがあなたとの出会いなのだから。
──物語は加速する。
いつからだろうか。
私が人と会わなくなったのは。
いつからだろうか。
私が此処に住んだのは。
いつからだろうか。
私が人では無い存在になったのは。
「はじめから決まっていた事なのかもしれないわね」
決まっていたのだろうか。
私が死へと誘う能力をもったことが。
決まっていたのだろうか。
私があれを殺す為に此処に来た事が。
決まっていたのだろうか。
……あの場所で彼女と出会う事が。
「決まる、ですか?」
春夏秋冬。
そして、春夏秋冬。
巡り巡って、春が来て。
いつのまにか、夏がやって来て。
一陣の風のように、秋が過ぎていった。
まるでそれが理かのように、冬が訪れる。
「ええ、何もかも。全て。」
はらりはらり、と桜が縁側に落ちてくる夜のこと。
それは諦め、だ。と妖忌は幽々子の虚ろな目を見て思ったのだった。
屋敷の庭に咲いた桜の木を彼女は見ていなかった。
その向こうの、それこそ妖忌すら見えない何かを、ずっと彼女は眺めている。
縁側に座って、桜の花びらが幽々子の懐を白に染めようとしても意に介さず、
ただただ、時がゆっくりと流れていた。
「花見ればそのいはれとはなけれども 心のうちぞ苦しかりける」
静かに、呟くように、
そっと彼女は紡いだ。
──桜の花を見ると、訳も無く胸の奥が苦しくなるのです。
「夜は冷えます。そろそろお休みになられた方が」
「……少しだけ、あと少しだけ。こうしていたいの」
妖忌はそっと頷くと、また静謐な屋敷へと戻る。
いつも笑っていた頃の彼女の面影を消し去るような、そんな夜だった。
◆ ◆ ◆
“それ”は、それこそまるで決まっていたかのように幽々子の身に降りかかったのだった。
人も妖も、全て平等に死へと誘う能力。
その能力に気づいた時には既に周りから見る目が変わっていた。
人でもない、妖でもない、それこそ神ではなく、地獄の使いと揶揄され、
幽々子の周りの人間は彼女の身を案じて、この屋敷にやってきた。
「死は、怖いのもの?」
一人。また一人。
布団に横たわって、顔に白い布をあてがった人間が増えていった。
それは紛れも無い死人であって、当時の幽々子でも些末ながらその死の香りを感じていた。
「ええ、怖いですとも。……けれど死は終わりではなく通過点と考えるようになりました」
私に剣を教えて。
庭師にそれを言ったのは何時の事だろうか。
能力ゆえに殺すのではなく。たゆみない精神力を以ってすればその死すら自分で止めることが出来るのはないか。
そう考えての決断だった。
しかしそれは焼け石に水であった。
結果的に言えばいくら庭師である妖忌から剣術を指南されたとしても幽々子の体では碌に剣を扱うことは出来なかったからだ。
「通過点?」
屋敷にやってきて、
春が来て。
夏が来て。
秋が来て。
冬が来て。
一年というものがどれだけあっという間で、それでいて儚いのものなのだと知り、
屋敷にいた人間はとうとう幽々子と庭師である妖忌だけであった。
それ以外は皆、死んでしまった。
病気も、寿命でも、なんでもない粛然たる死。有無を言わせない能力。
「ええ通過点です。死ぬ前に良い事をすれば天国に。当然悪いことをしていれば地獄に連れて行かれるのだと、聞いたことがあるのです」
妖忌の言葉は力があって、重みがあった。
庭師である彼は幽々子の生まれたころから見守っているのだから。
「私は……。天国に逝けるのかしら」
それはひどく震えていたと思う。
空を見上げて、微かな嗚咽感を必死に我慢して。
声にもならない声で、妖忌ですら見たことのない表情で。
気丈に振舞っていた彼女の、初めての涙だった。
──それからまた春が来て。夏が来て。秋が来て。冬が来て。
幽々子は屋敷の縁側で、思うのであった。
「西行妖」
その名前を呟いて、虚ろなその瞳に力が宿る。
一際大きい桜の木。八雲紫と出逢った場所。
桜の花を咲かせないあの木が普通の桜の木では無い事は分かっていた。
「ねえ、桜の花はどうして鮮やかな薄紅色に染まるのかしら」
言葉を投げかける。
そうすれば誰かが、返してくれるような気がしたからだ。
けれどその言葉は宙を舞い、風に攫われるかのように消えていった。
「……それはね。人の血を吸っているから綺麗な花を咲かせるのよ」
ひどく暗い声だった。
それが自分から発したものだということに気づき、寒気がした。
西行妖。それこそ幽々子の目的だった。
何故ならば西行妖と呼ばれる、花を咲かせない桜の木の下で、西行法師は死んだのだから。
賭けである。
死へと誘う少女と、
死を招く桜の木と、
どちらが本当の死せるものなのか、どちらが果たして本当の化け物なのか。
復讐であって、復讐ではないなにか。
言うなれば、歪んだ使命感。
「どうせ地獄へ行くのなら、せめて最後まで」
そして桜の木を睨みつける。
全ては決まっているのだから。
◆ ◆ ◆
夜。
それは人々が眠りに就き、妖怪共が跋扈する時間だった。
妖忌が寝ているのを確認して、幽々子は深い闇へと身を乗り出した。
目が暗闇に慣れておらず、辺りが真っ暗であったが、それでも彼女は軽い足取りで其処へ向かった。
幽々子の白い装束は寝るときに着るものであったが、誰もが寝静まった暗い夜には綺麗なほど白く輝いていた。
天女のように見えるそれは、すたすたと足を止めることなく、目的地まで歩き続けた。
「御機嫌よう。ここに貴女が来ると思っていたわ」
其処に着いた時には既に彼女はいた。
赤いリボンで隙間を結んだ上に座って見下ろしている八雲紫が、いた。
さらりとした艶やかな金の髪が靡くたびに、透き通った白い肌が晒されている。
それを意に介さず、くすりと幽々子に対して笑みを浮かべて手を振るのだった。
「私も思っていたわ。紫」
紫の笑みに、幽々子も笑みを浮かべて返す。
紫を見上げると思わずにはいられない、西行妖が、そこにはあった。
桜の花を咲かせない大きな木が、八雲紫の背に雄々しく生えていた。
西行妖の、圧倒的な存在感に息を呑む。
「ねぇ、幽々子」
そんな幽々子の心情を知ってか知らずか、紫は楽しげに話を進める。
「もしこの桜の木が満開になったら。その時は一緒に花見をしましょう?」
もし、この桜の木が満開になったら。
それはなんて綺麗な花が見れるのだろうか。
それはなんて甘い誘いなのだろうか。
勿論、紫は知らないのだろう。
目の前にあるのが、ただの桜の木ではなく、血を飲みすぎた妖怪だという事を。
そしてこの西行妖は花を咲かせないことを。
「そうね──。」
言えなかった。
この桜の木は花を咲かせないわ。
その一言が、言えなかった。
「他の桜は散っているのに、この大きな桜の木は、まだ花を咲かせないなんてね」
不思議そうに呟く彼女を、見ることが出来なくて、
そっと視線を西行妖に向けて、
桜の花を咲かせない西行妖が、眠っているように見えたのだった。
西行妖が眠っている。
そう思った幽々子であったが、あながち間違いでは無いのではないかと考える。
では、この桜が開花した時、一体何が起こるのだろうか。
一抹の好奇心と、不安が同時に沸いて出てきた。
……眠っているのならば、起こせばいいのだ。
その対価が何になろうとも、私はこの目で西行妖の開花を見てみたくなった。
興味が、好奇心へと変わり、紫の言ってる事を聞き流してしまうくらいに、魅力的なものへと変わっていった。
「それでね、藍がね──」
「決めた」
紫の声を遮って、彼女は紫に笑みを見せて、そして
「私がこの西行妖の花を咲かせてあげる」
それが何を意味するのか、幽々子にも、ましてや紫にも分かっていなかった。
紫はそんな幽々子の声色から不穏な気配を感じたという事だけ。
そして、幽々子が桜の魅力に取り憑かれたそれに、似ているようなそんな気がした。
◆ ◆ ◆
「……」
その頃、魂魄妖忌は静かに目を開けて音も無く立ち上がった。
動きには無駄が無く、庭師というよりは武士というような風格を持つ彼は、溜息を一つついて懐にあった刀を拾い上げた。
幽々子を護る彼は勿論、幽々子が屋敷を出て行った事に気づいていた。
け ど妖忌が寝ている事を確認してから出て行ったことが気がかりで、そんな彼女を 邪魔をしてはいけないと思い、外出について話に触れなかったのだった。
いや、触れられなかった。
嬉々として外へ、闇へ足を踏み入れる彼女を、止めることが出来なかった。
待って下さい、と言えなかった。
ご一緒によろしいでしょうか、とも言えなかった。
「……」
けど、どういう風の吹き回しか分からないけども、
妖忌はおもむろに幽々子の後を追うことにしたのだった。
「西行妖」
一言、そう呟いて暗闇の中、足を一層早める。
春の季節。桜の季節になっても、花を咲かせない桜の木。
あまりにも血を吸いすぎた桜の木。
彼女はそれを何度も見上げ、眺め、そして何を感じたのだろうか。
「……」
いつかはこうなるのではないか。
妖忌は彼女の成長を見守るにつれて、そんな事を思っていた。
いつかはこうなってしまうのではないか。
そんな思いはやがて、現実となり、少しの好奇心が後押しして、彼は向かおうとしている。
どこに。西行妖に。
どこに。幽々子殿の元に。
ん?
おかしい。
何かが、おかしい。
……彼女が西行妖に近付いたとして、一体何が起こるというのだ。
いつかはこうなってしまうのではないか。
それはどうなってしまうのか。
そんなことを考えようとしたとき、少女の楽しげな声が聞こえた。
はっと気づいて妖忌は眼前の光景に目を凝らす。
彼の目にまずもって映ったのは大きな桜の木。西行妖が妖忌を見下ろしていた。
そして次に映ったのが、幽々子と紫の二人。
妖怪と人間が楽しく話している。耳をそば立てて聞く限りでは紫が一方的に話しているように見えるが、
遠い場所からそれを見ている妖忌にはよく分からなかった。
幽々子の背中を見て、彼は一人思うのだった。
いつも彼女の傍にいた妖忌だが、こんなにも彼女の背中は大きかったものだろうか。
成長して、大きくなった彼女は、何人ものの死を背負って生きている。
そんな彼女を独りにはさせたくない、そう思った妖忌であったが、
彼女と紫の姿を見て、もう十分ではないか、と思わずにはいられなかった。
私がいなくなっても、彼女は生きていけるのではないだろうか。
手を貸してやらないと足取りもおぼつかない彼女が転んでしまいそうで、
誰からも恐れられ、蔑まれた彼女が不憫でならなくて、
そしてなにより、彼女が好きだったから。
だから妖忌はずっと彼女の傍にいよう。そう思った。
「……」
けどその必要はないのかもしれない。
妖忌は来た道を振り返って、静かに屋敷へと帰っていった。
◆ ◆ ◆
これは彼女なりの決意だったのだろう。
紫は事の顛末が終わったとき、そう結論付けた。
「私がこの西行妖の花を咲かせてあげる」
その言葉が意味することを、まだ知らなくて。
そういえば、この桜の木に花を咲かせたら花見をしようかと言ったからかしら。
……なんて事に思い至った。
だから無責任にも、彼女は言ってしまうのだった。
「楽しみにしてるわ」
その時の幽々子の表情は、一体どんな表情をしていたのだろうか。
呆れた、のだろうか。
それとも、哀しかったのだろうか。
「それじゃ、また会える日まで」
あまりにも、唐突過ぎる出来事に。
背を向けて、去っていった彼女を見て。
これが何を意味しているのか、それ以前に、
彼女に何があったのか、それが知りたかった。
「……」
呆然。
何がなんだか、分からない。
「……紫様」
幽々子の背をずっと目で追った紫の背後で、西行妖は嗤った。
そんな気がした。
◆ ◆ ◆
「幽々子殿は誰とも会いたがっていないようだ。私も含めて、な」
次の日の朝。
人間が朝目覚めて、すぐの時間に紫は幽々子の屋敷へと出向いた。
屋敷の中へ隙間を使って入らなかったのは、幽々子に嫌われたく無かったという事もあり、
屋敷の前まで隙間でやってきて、玄関先で彼女は妖忌にぴしゃりと言われたのだった。
「……そう」
会いたがっていない、という妖忌からの言葉は真実味に欠けていたが、妖忌自身にも会いたがっていないとなると、
それこそ余計に、それが事実なのだと突きつけられた気分になった。
「そうだ、あの大きな桜の木の事について聞いてもいいかしら」
そして、幽々子の口から語られないのであれば、
彼に聞くしか無かった。気になっていたことを。
きっとそれは彼女に関係するものなのだろうと。
「いいだろう。ただ条件がある」
「条件、ですって?」
「幽々子殿を、見捨てないで欲しい」
一体何の条件を出されるのかと思って身構えた紫であったが、
全くの想定外の条件に驚いた。
そんな条件など、条件とは言えない。
私は千年を超える妖怪であって、彼女は人の子なのだから。
「ええ、見捨てないわよ。だって私の友達なのだから」
そう、彼女は人の子なのだから。
それから妖忌は幽々子の生い立ちを語った。
彼女自身が特異な能力を持った少女である事や、この地へやってきたことも。
そしてこの屋敷に幽々子と妖忌しかいない訳も。何もかも。
妖忌はどこか懐かしさを感じながら語り、紫はそんな妖忌に口を挟まずに黙って聞いていた。
聞いていくに連れて、紫の知らない彼女が妖忌の中にはいたという事を知った。
彼女は、私にどんな姿を見せていただろうか。
彼の語る中で、それこそ無邪気な子供のようなしぐさを、笑顔を見せただろうか。
私に向けた、笑顔はどこか大人びていて、そして……。
よく、分からない。
「最後に、西行妖について話しておきたいことがある」
西行妖というワードを耳にした途端、不思議と傘を握っていた手に力が篭った。
恐らく心の片隅で語られるであろうと思っていたからかもしれない。
だからこそ前に妖忌と話した時に鎌をかけていたのだが、あの時はひっかからなかった。
それを今、私に話すということは彼は僅かでも自分を信頼しているということだろうか。
「一際大きな桜の木があるのは、知っているな。あれは桜の木ではあるが、同時に妖怪でもある」
信頼、というものを私は築けたのだろうか。
それもよく分からない。
「……血を吸いすぎた、妖怪なんだ」
◆ ◆ ◆
「それはつまりあの桜の木は幽々子と同質の能力を持っているというの?」
「おそらく、な。あの桜の木は今まで何故か幽々子殿に危害を加えていなかったか ら安心しきっていたが、一応紫殿にも知っていて欲しかった」
死へと誘うのと同質の能力。
あの桜の木もまた、死の能力を持っているのだろう。
血を吸いすぎた故の、忌まわしい謂れの力。
花を咲かせないというのは、つまり死を象徴しているのだろうか。
「ありがとう。何か掴めた気がするわ」
「死」というキーワードが溢れかえり、死が軽いもののように思えてならなかった。
平然と、目の前にあるというのに。それは少し前にいて笑っているのだ。
追いつくことも追いつかれることもない距離。
彼女は、西行寺幽々子は、一体何を考えているのか。
それは桜の木と関係しているのだろうか。
『私がこの西行妖の花を咲かせてあげる』
ふいに彼女の言葉が過ぎった。
あの妖怪桜を咲かすという事が何を意味しているのか、気づいて。
妖忌と別れた後、すぐさま隙間を使って移動したのだった。
「それはあまりにも無謀だわ……!!」
焦りに混じった呟きが、隙間の中へと消え去った。
◆ ◆ ◆
隙間と呼ばれる虚空の闇へと消えていく八雲紫の背を、妖忌は目を細めながら眺めていた。
あの暗い闇の向こうには何があるのだろうか。
少しだけ気になって、やめた。私はあちらに行ってはならないと思った。
行ったところで何になるとも、思った。
彼女の言葉には、少なからず「貴方は此処に居るべき」という思いが込められていたような気がする。
自惚れかもしれないが、そう感じたのだった。
そして感じたのであればやるしかない。
「私に時間があれば」
けど、それは難しいことのようにも思えた。
それは突然やってくる。段階を踏まずに、何かがキッカケでとかそういうのを無視して、いきなり現れる。
だからきっと余裕が生まれてしまうのだろう。段階を踏んでないが故に「きっと大丈夫だろう」というありもしない余裕が。
もしかしたら、それが妖忌の行動にも現れているのかもしれない。
「時間など、とっくの昔に無くなっていたのだったな」
寂しげに語る庭師が空を仰ぐ。
陽射しが眩しくて手で目を覆うようにしたが、覆うことが出来なかった。
手のひらからすり抜ける感覚に、妖忌は溜息を呟いた。
◆ ◆ ◆
「君がやってくるなんて思っても見なかったよ。ん、急ぎの用かい?」
「貴方とゆっくりお話したいところだけど、生憎、急を要するのよ」
紅。
八雲紫が隙間を使ってやってくた場所は紅に囲まれた大きな部屋だった。
頭上には大きなシャンデリア。灯る火はゆらゆらと規則正しく燃えていて、それが魔法によって制御されていることが分かる。
とん、ふかふかの絨毯に降り立って紫は目の前にいる人物に願い出た。
「図書館を使わせて欲しいの」
「いいだろう。その代わり一つ頼みたいことがある」
「それが私に出来る事なら、ね」
目の前の人物がくすりと笑って、手をあげる。
図書館を好きに使え、というサインに紫は顔を綻ばせて、くるりと振り向いて隙間へと消え去った。
……勘繰り過ぎではないだろうか。
彼女だって、紫と会いたくない時だってあるのかもしれない。
それが重なってしまっただけでは無いのか?
そんな考えが思い浮かんで、首を左右に振ってかき消した。
幽々子が行おうとしている、咲かないものを咲かす、その行為だけで危険なのは確かだった。
生あるものを必然的な死へと招く、ならまだいい。その死というものが生の延長線上に存在しているのだから。
しかし逆はどうだろう。死から生へ、それはとても危険な事だ。
どんな物語にも、生き返すにはそれ相応の代償を求められる事が多い。
西行妖に咲かせる代わりに幽々子が代償として死に至る可能性があるのかもしれない。
そしてそれを彼女は知っているのだろう。死へと誘う少女ならば、生死すら操れると踏んでの行為かもしれない。
ならば紫は止めなくてはいけない。彼女の友達として。何より、二番目の親友まで離したくなかった。
八雲紫の妖怪としての力は強いとは言い切れなかった。
力でも負ける。妖力でも負ける。
境界を操る、という一点のみで何とか生きてきた。
それでもきっと、幻想の妖怪には負けてしまうかもしれない。
西行妖と言われる妖怪には歴史がある。
歌聖と呼ばれた男があの木の本で死に至り、そしてその繰り返しだ。
何人も、何人もの血を吸った妖怪桜。その力は計り知れない。
封印する。
何も起こる前に、彼女が動き出す前に。
「私がもっと強くなれば、守れるのかしら。」
彼女を。
「見つけた」
大量の本に囲まれながら、紫は目的の本を見つけることが出来た。
これは大量の桜の花びらから一つだけ色が違う花びらを捜すのと同じくらい難しいもので、
自分自身、簡単に見つからないだろうと高を括っていただけに、その本を見つけたときに思わず声を上げてしまった。
焦りに混じった声が震える。頭がいつも以上に働いて、鮮明に、よりクリアに思考することが出来る。
その本を手にとって、マヨヒガへと帰る。
それでもそれが杞憂であって欲しい。
そして早く、あの桜の木を封印させなければならない。
本を握り、奥歯を噛み締めた。
◆ ◆ ◆
──いつまでも続くと思っていた。
ううん、違うわね。
私は目を反らす事が出来ずにいるのだから。
だから、だから、私はこの場所にいるのだろう。
あの日々を続かせる為に、けじめとして、終止符を打たなければならない。
いつの間に長き眠りの夢さめて 驚くことのあらんとすらむ
私はいつまで彷徨って、迷い続ければいいのだろうか。
いつになれば、私は。
◆ ◆ ◆
「……」
夜の帳から徐々に明るくなっていく丑四つ時。
妖忌は微かな物音が玄関先から聞こえて目が醒めた。
元々浅い睡眠だったせいか、意識はすぐに覚醒しその物音が幽々子のものであると推測した。
朝食も夕飯も彼女と食事を共にすることが無く、幽々子の部屋の前に食事を置いていたため、今日一日、彼女をしっかり見てはいなかった。
だからだろうか、いつもの外出にさしてまた紫と会うのだろうかと思っていたが、今回ばかりは妙な胸騒ぎがした。
胸を締め付けられるような、ひどく気持ち悪い何か。
その正体はきっと、焦りだ。
焦りが、妖忌を急かし、そして苦しめる。
何をもたもたしているんだ。早く幽々子を追え、と思い至った時には妖忌は腰に刀を提げて翔けていった。
屋敷から出た時には既に幽々子の姿は無かった。
目を凝らして辺り一体を眺めても闇しかなく、彼女はもしかしたら走っているのか、という事を考える。
きっと彼女は西行妖の元へ向かっているのだろう。だとしたら行くべき道は一つだった。
「……」
でも、幽々子の元に追いついたとしたら。
私は何が出来るだろうか。
何をしてあげられるだろうか。
彼女に対して、何も出来ないのではないか。
妖忌は大きく深呼吸して、冷たい夜の空気が彼の頭に鞭を打つ。
たとえ何も出来なくても、彼女の傍に居てやれる事なら出来るだろう。
山桜が咲き誇るなか、妖忌は走った。
桜の花びらが走っていく妖忌をすり抜けて宙に舞う。
体が悲鳴を上げる。足が鉛のように重くなって熱を帯びる。夜の冷気が顔面に突き刺し頬が動かなくなっていく。
走るのを止めたらもう彼女と会えないのではないかという錯覚を覚えて、ただがむしゃらに走った。
走って走って走って、
妖忌は少しだけ昔の事を思い出した。
「──私は、どうしたらいいのかしら」
あれは、彼女の父親が死んだという報せを聞いた時であったか。
幽々子の父親は彼女が幼い頃に旅立ってしまったのだから、最初にその報せを聞いた時は表情を崩さず「そう……」と返しただけだった。
肉親を無くしたという実感が無かったのかもしれない。
け ど少し経って、妖忌に向かって「……もう会えないのかしら」と嗚咽混じりにそ う聴いてきたときは、自分自身何と言えば良いのか分からなかったのを覚えてい る。
そして死の儚さと無情さを身を以って知った彼女は、あれ以来人と接することが少なくなった。
「それは……、私にも分かりませんな」
それを聞いて彼女は顔を俯かせた。
でもこればかりは妖忌自身が分かるものでもないし、何といっても彼女自身が解決すべき問題だと思ったからだった。
だから妖忌はぶっきらぼうに彼女に告げたのだった。
「ですが、幽々子殿は独りでは無いことをお忘れなきよう」
その言葉に呆けた顔を見せて、そしてその意味を理解し、はにかんだ笑顔で幽々子は「ありがとう」と言った。
柄にも無い事を、と。恥ずかしくなって妖忌は背を向けて早々と立ち去った。
後ろからはくすりと笑った声が聞こえて、気恥ずかしさと安堵感が彼の胸を一杯にさせた。
そんな事を思い出した。
「────」
西行妖が蕾を実らせていた。
いやそれよりも先に、西行妖の幹の元で倒れている人影に目がいった。
白い着物を着た、彼女が。
西行寺幽々子の姿が、そこにあった。
「幽々子殿……?」
足が止まった。
足よりも先に震える手が前に出て、バランスを崩して地面に手をついて、はっとして顔を上げる。
頭が真っ白になった。
思い出していた懐かしい記憶とか、そんなものを上から白で塗りつぶしたように。
妖忌は何度か転びそうになりながらも、幽々子の元へ駆けつけた。
「ゆゆ……こ……?」
彼女が着た白い着物に紅黒い色を見た時に、これは何だと思って、少し時間が掛かって理解して、思わず幽々子の手を握った。
夜の冷気を纏った妖忌の手は冷たく、彼女の手を握ってもそれが暖かいのか冷たいのか分からなかった。
感覚の無い手で握り締めながら、彼女の姿をもう一度見る。白の着物のそれは、まるで死装束のようだ、と思った。
「……妖忌の手、冷たいわ」
今にも消えそうな声で、彼女は言った。
笑みを作るように頬をぎこちなく動かして、彼の手を握り返した。
「なにして──」
「私、駄目だったわ」
妖忌の声を遮って、幽々子は笑みを作ったまま西行妖と妖忌を見上げながら話し始める。
「桜の誘惑に、負けたの」
桜は人を呼び寄せる。
桜に人がやってくるのではなく、桜に魅了されて人はやってくる。
そんな事を聞いたことがあった。
でも分からなかった。今になって彼女が桜に魅了される理由が。
西行妖が原因ならば、何で今なのか。
その最たるきっかけが分からなくて、何でこうなってしまったのかと考えて、
妖忌の心の内で答えが出ないのを見透かしたように、彼女は続けた。
「この桜が咲いたら、花見をしよう。って約束したの」
誰と。
と言おうとして、八雲紫の姿が思い浮かんだ。
そういえば彼女の姿が無い。今日に限って来ないとは思えなかった。
紫は幽々子の事を気にかけているようだったし、何より心配している節があった。
あっという間に空間移動出来る彼女ならば、私より先に彼女の元に駆けつけていたのではないかと思った。
「でも、やっぱり駄目だった」
弱弱しく話す彼女が見ていられなくなって、彼女を抱きしめた。
冷たい身体同士、そこには何も感覚など無かった。
妖忌の体は冷え切っていて、そして彼女の身体も冷え切っていた。
「妖忌」
「……」
「ありがとう」
思いがけない言葉に、待ってくれ、と思った。
だから彼は単刀直入に訊いたのだった。
──死んでしまうのですか?
──そうね、そうかもしれない。
「ふざけないで下さい、幽々子殿……!! 私が助けますから。助けるから……」
「ねえ妖忌、西行妖は咲いているかしら」
抱きしめていた彼女をそっと放して、西行妖を見上げる。
蕾ばかりで、一つでも花を咲かせていないかと目を動かして、必死に探す。
けど依然として、花を咲かせることは無かった。
「咲いて、無いのね」
彼女の身体が動かないのを見ると、動かせないほどに衰弱しているのだろう。
目は薄っすらと閉じかけていて、声を発するだけで辛そうな彼女を見てはいられなかった。
「願はくは、花の下にて、春死なん……」
彼女の紡ぎだす言葉に、必死に耳を傾ける。
一言も聞き漏らしてはいけないと思って、思わず幽々子の手を強く握る。
彼女の声を聞かずに無理矢理でも屋敷に戻っても助かる保障なんて無かった。
既に彼女の着物を染めている血は妖忌の着物にも染みこんでいて、とても助かるなんて思えなかった。
「その如月の」
だから無言で彼女の言葉に頷くしかなかった。
ただただ、頷くしかなかった。
「望月の頃──……」
その短歌を詠い終えて、彼女は、もう声が出ないのであろう。
あ、り、が、と、う。
そう口で形作って、微笑んで、微笑んで……。
──彼女、西行寺幽々子は息を引き取った。
何も言えなかった。
何も、言えなかった。
「幽々子殿……、幽々子殿……!!」
こうもあっさりと、終わってしまうものなのだろうか。
彼女の命はこうも簡単に消えてしまうのだろうか。
「お願いですから、手を握り返してください……」
安らかな死顔だった。
血を流して、痛かっただろう。寒かっただろう。
そんな中で彼女は笑んだまま逝った。
幸せそうに笑う彼女が、ひょっとしたらまた起き上がるんじゃないかと思って。
けど彼女の赤が現実を突き付け、とうの昔に枯れたと思っていた涙が溢れ出てきた。
◆ ◆ ◆
杞憂でもなんでもなかった。
奇しくも紫の嫌な予感は当たってしまった。
「何よ……これ……」
西行妖が、咲いていた。
満開の花は、薄紅色に染まり。ぼう、と怪しげに灯る光に、紫は不安を覚えた。
少し歩を進めると西行妖の下で倒れている人影があった。
それが何なのか考えるよりも先に、足が動いた。
「……ゆゆ、こ?」
訳が分からなかった。
彼女は何で笑ったまま動かないのか、
何で彼女の傍にいる妖忌がずっと泣いているのか。
あまりにも唐突な出来事に頭がどうにかなってしまいそうだった。
「満開よ、ねえ。ここで花見をするんじゃなかったの……?」
声が震えて、手の先が冷たくなっていく。
頬を引き攣らせて、彼女を、動かなくなった彼女を見下ろす。
──遅かった。
何もかもが、遅過ぎで手遅れで、そして全てが終わった後だった。
心にぽっかりと穴が開いたかようだった。
大きな空洞が出来てしまったかのような虚無感。
もしかしたら妖怪は、ほんとは中身等無いのかもしれない。それくらい伽藍洞で何も無かった。
死とは、唐突に訪れるものなのだと。
死とは、もう彼女と話すことは出来ないの事なのだと。
死とは、こんなに悲しいものなのだと。
今更になって、知った。
紫はおもむろに満開の西行妖を見上げて、やり切れない思いを抱いて、拳を握り締めた。
花を咲かせた西行妖は、死んだ幽々子を糧にしているように見えて、そして、新たな死に喜んでるように見えて。
だから許せなかった。
「──これ以上、こんな悲劇を繰り返さないように」
西行妖を、封印する。
それが亡き友に対するせめてもの罪滅ぼしだった。
# 行間。
桜が、舞っていた。
風が、吹いていた。
髪が、靡いていた。
「この桜の木は、花を咲かすことはあるのかしら」
女性の麗らかな声が誰かに問い掛ける。
肩に舞い落ちてきた桜の花びらを、軽く手で払い落として、彼女の眼前にある大きな桜の木を見上げる。
他の桜の木とは違う、大きな幹。力強いそれは、けれど桜の花はおろか、蕾すら生っていなかった。
だから、だろうか。
この桜の木の花を見てみたくなったのは。
或いは、怖いもの見たさに、でもあるのかもしれない。
花を咲かさない、というよりは、咲かせられないのではないかと考えた。
だからそこには、理由というものが存在するわけで。
退屈な毎日を少しだけ鮮やかな色で染めてみよう。そう思った。
「ねえ、妖夢。頼みたいことがあるのだけれど……」
◆ ◆ ◆
「紫様」
「……」
「魂魄妖夢が動き出しました」
「……」
「春を集めているそうです。桜の木を咲かせる為に、と」
「……そう」
報告する藍に背を向けるように、紫は布団で寝ていた。
春と聞いて、もうそんな季節なのかと思って、時が経つのは早いものだと感慨深くなる。
「……いいのですか?」
「……」
「このまま彼女達を放っておいて、幽々子様が──」
「そうだ、藍」
藍の言葉を遮って、紫はさっきまでおぼろげに話していた口調から一変。鋭い声が藍を刺した。
その反応に藍は驚きを隠せずにはいられなかった。
「なんでしょうか」と声を絞り出す。
「花見の準備、しといて」
◆ ◆ ◆
これから、だ。
"彼女は"心中で呟いた。
≫next history...
#胡蝶の幻想: あとがき
お久しぶりです。
前回の話を書き終えてから四ヶ月ほど経ってようやく今回のお話が終わりました。
今回のはAnotherStoryで書かれていたものをリメイクしたもので、台詞だけだった描写に地の分を加えたり、
リメイク前を読んでいた方も満足出来るように「DifferntStoryでの胡蝶の幻想」を意識しました。
っと。
……実はリメイクだけあって、語れる部分が何も無かったりで。
あとがきのスペースをどう活用しようか迷ってます。はい。
そんな訳でして、遅筆ながらも今後も見守っていただけると嬉しいです。
こんなに書くペースが遅いと、はやくネタバレしたくなってしまいます・・・w
筆者自身の葛藤とはさておき、
そろそろこの話も中編、後編へと向かっていきます。
短編集なのに前半後半あるんかい!と思われる方もいらっしゃいますでしょうが、
一本の糸に紡ぐように、物語は収束していきます。
これからどうなっていくのか、私自身楽しみです。
(まあそれ以前に大学受験という関門が控えてるんですけどね……)
10/11/07
17:47 影猫記。
|